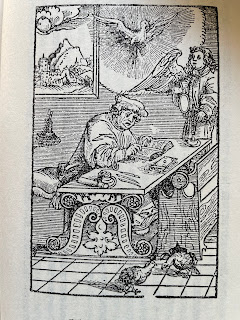|
昨日、私は高校の同窓会に5年ぶりに出席するため新橋まで出かけました(3年間ほどコロナ禍のため、実施されず、昨年は実施されたようですが、たまたま私には案内が来ませんでしたので欠席していました)。前日まで、先週の土曜日からの二泊三日の郷土帰りの強行軍が災いしてか、体調がずっとすぐれず何度も行くのを断念しようと思いました。結局、土壇場まで、逡巡に逡巡を重ねながら、勇を鼓して出かけることにしたのです。結果は、幸い体も守られ、かえって元気が与えられ、家に帰って来ました。出席者は私をふくめ21名(男性16名、女性5名)でした。
都合三時間の間を利用してそれぞれが近況報告をしました。普通の集まりと違って。お互いに同年なので、今更、歳を経たことの苦しさを訴えるでもなく、その置かれた状態でどのように今生きているかの証、それに互いが耳をそばだてる集いだったように思います。それはもうほとんど全員が八十余年の年月を経て満身創痍の身であり(たとえ自分は健康であっても配偶者が健康を失っていたりしている場合もあり)、そのことにおいては一人の例外もないからであります。
分けても寂しく思わされたのは、やはり多くの物故者のお名前を知らされたことでした。それぞれの方との関わりを思い出すにつけ、それらの人々とはもはや語り得ない、もう逝ってしまったという寂寥感は覆うべくもありませんでした。特に生前元気であり、会の主メンバーの一人でもあったM氏が10月に亡くなり、彼の奥様が写真をもって我々の集まりに「主人が喜ぶだろう」と言って参加されたのには、痛々しい思いがしました。もちろん、皆さん、奥様の来会を喜ばれ、それぞれが同君との思い出を語る貴重なひとときとなったことは言うまでもありません。
一方私は、何とか同窓生の方に、「イエス様は、私たちのように座して死を待つばかりになっている人間に、ご自分のいのちと引き換えに永遠のいのちを与えてくださったお方だ」と個人的にご紹介したいと思っていましたが、そのような機会は与えられませんでした。
ただ、皆さんと三々五々別れる時に、以前から私に「福音」について聞いてこられた方が今回の同窓会にも出席されていましたので、その方にだけは「死は終わりではない」というベック兄のメッセージの載っている小冊子をお渡ししました。私としては、何とかその小冊子がその方にとって「福音」となるようにと祈るばかりです。
このように、わずか三時間の同窓会でしたが、来年度の幹事は早速その場で決められ、今日は今日で、手際良く、昨日の会計報告がメールで送られて来ました。今、私は許されれば来年の同窓会にも、出席したいと思わされています。冒頭、11月の末日に当たり、考えさせられる点がありましたと述べましたが、過去のブログ記事をこの機会に再読してみて、忘れていることばかりで、その時には切実に思い、決心して同窓会に出席していたのに、今ではいい加減になって、すっかり初心を忘れていることを自戒せざるを得ませんでした(※)。
※https://straysheep-vine-branches.blogspot.com/2013/12/blog-post_9.html
覚えていなかったのですが、上記ブログでM氏について少し触れていたのです。そこから換算するとM氏はまさに10年余り、病に伏しておられたことになります。
https://straysheep-vine-branches.blogspot.com/2018/06/blog-post_23.html
罪から来る報酬は死です。しかし、神の下さる賜物は、私たちの主キリスト・イエスにある永遠のいのちです。(新約聖書 ローマ人への手紙 6章23節)
もし、私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは、すべての人の中で一番哀れな者です。しかし、今やキリストは、眠った者の初穂として死者の中からよみがえられました。(新約聖書 1コリント15章19〜20節)